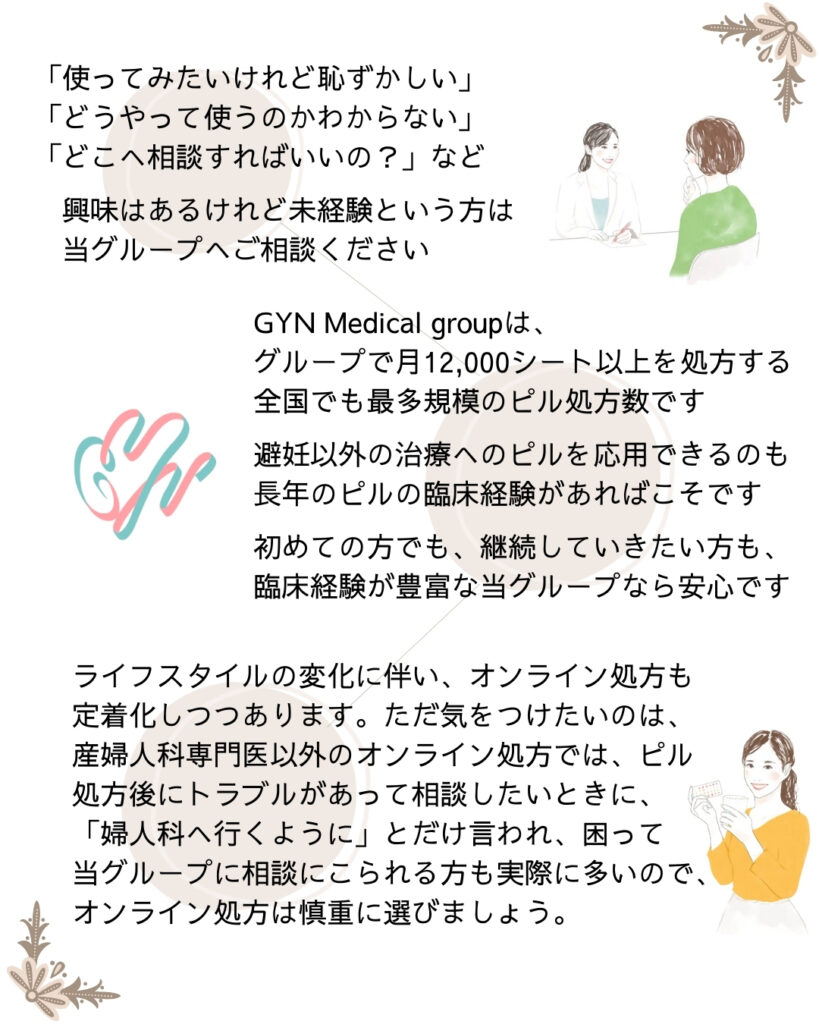ピルは排卵をストップし、子宮内膜の増殖を抑える作用があります。
排卵は妊娠を希望するとき以外は必要ないので、ピルで人工的に排卵を止めることは特に問題ありません。むしろ排卵や生理を繰り返すことは女性の身体にとって大きな負担となり、子宮や卵巣の病気の原因にもなることから、ピルの服用で排卵を抑えることは子宮内膜症や卵巣がんをはじめとする婦人科系疾患の予防にも役立つと考えられています。
(現代女性は出産回数が少なく生理期間も長くなるので、子宮への負担が大きいといえます。)
ピルには避妊以外にも女性の強い味方となる以下のような副効果が期待できます。
- 生理痛・過多月経の緩和
- 生理不順の改善
- 月経前症候群(PMS)の緩和
- 大人ニキビ・多毛改善
- 更年期症状・プレ更年期の改善
- 卵巣がん・子宮体がんの予防
- 月経移動(生理日のコントロール)
ピルを上手く活用することで、女性のQOL向上にも大きく役立ちますが、ピルの普及率は10%台とまだまだ低く、多様なメリットがあるのは分かっていても、ピルを使ってみたいけど不安感がある人も多いのではないでしょうか。
そこでピルに関することで特に気になる関心事をまとめてみました。
01ピルの副作用(吐き気、頭痛、体重増加、血栓リスク、性欲低下など)
02ピルの安全性(長期間使用しても問題ないの?健康への影響(メリット・デメリット)は?)
03生理への影響はあるの?(生理周期の安定、経血量の変化、生理痛の軽減)
04ピルの避妊効果としてどのくらいの確率で避妊できるの?(成功率・避妊のメカニズム・他の避妊法との比較・避妊効果が落ちる原因)
05ピルの服用が将来の妊娠に与える影響は?(ピルをやめた後の妊娠しやすさ・排卵はいつ再開?将来の妊娠に与えるメリット・やめた後に妊娠しづらいケースは?)
06他の薬との飲み合わせで注意すべきなのは?(避妊効果が低下する薬・併用注意の薬・サプリとの相性)
今回は、
【1】ピルの副作用(吐き気、頭痛、体重増加、血栓リスク、性欲低下など)
について解説します。
ピルの副作用には軽度なものから重大なものまでさまざまあります。
1)吐き気・嘔吐
【原因】
- ピルに含まれるエストロゲンが胃の粘膜に影響を与えるため
- 飲み始めのホルモン変化による一時的なもの
【対策】
- 食後に服用(胃への負担を軽減)
- 就寝前に飲む(寝ている間に症状が和らぐ)
- 数週間続けて様子を見る(体が慣れてくると軽減することが多い)
2)頭痛・片頭痛
【原因】
- ホルモンバランスの変化で血管が拡張・収縮するため
- 特にエストロゲンの増減が影響
【対策】
- 水分を多めに取る(血液循環を良くする)
- 超低用量ピルや黄体ホルモン単剤(ミニピル、生理痛があればジエノゲスト)に変更する。
- 片頭痛持ちの人は、血栓リスクがあるので天然型エストロゲン(アリッサ)含有ピルに変更をお勧め。
3)体重増加・むくみ
【原因】
- ホルモンの影響で水分を保持しやすくなる
- 食欲増加による体重増加
【対策】
- 塩分を控えめにする(むくみを抑える)
- 適度な運動を取り入れる
- 数ヶ月様子を見る(体が慣れてくると体重変化が落ち着くことが多い)
- むくみがひどい場合は、第4世代ピル(ヤーズ)やアリッサ、黄体ホルモン単剤に種類変更を検討する。
4)血栓症リスク(深部静脈血栓症、肺塞栓症など)
【原因】
- エストロゲンが血液凝固を促進するため
- 血流が滞ることで血の塊(血栓)ができやすくなる
【リスクが高い人】
- 35歳以上で喫煙習慣がある人
- 肥満・高血圧・糖尿病がある人
- 家族に血栓症の既往歴がある人
- 長時間の座りっぱなし(飛行機・デスクワーク)
【症状(要注意!)】
- 足の痛み・腫れ(特に片足のみ)
- 息切れ・胸の痛み(肺に血栓が飛ぶと危険)
- 突然の視力低下や頭痛
【対策】
- 長時間同じ姿勢を避ける(定期的に歩く)
- 水分をしっかり取る(血流を良くする)
- 禁煙する(喫煙×ピルは血栓リスクが大幅に増加)
- 黄体ホルモン単剤(ミニピル、ジエノゲスト)や天然型エストロゲン(アリッサ)含有ピルへの変更を推奨。
血栓症リスクは特に気にされる方が多いですが、ピルの副作用で血栓ができる確率は「0.05%」程度です。やっぱり血栓ができる可能性があるんだ、と思われる方もいるかもしれませんが、実は、妊婦さんはこの確率の約7倍の確率で血栓ができるといわれています。
血栓ができることを気にして妊娠される方はあまりいらっしゃらないと思います。過度に気にし過ぎないことが大切です。
5)乳房の張り・痛み
【原因】
ホルモンの影響で乳腺が刺激される。
【対策】
数週間で慣れることが多い、痛みが続く場合は医師に相談。
6)気分の落ち込み・抑うつ
【原因】
ホルモンが脳内のセロトニンに影響する。
【対策】
男性ホルモン活性の抑制に起因することから、第2世代ピル(ラベルフィーユなど)への変更を推奨。
7)性欲の低下
【原因】
ホルモンバランスの変化によるもの。
【対策】
男性ホルモン活性の抑制に起因することから、第2世代ピル(ラベルフィーユなど)への変更を推奨。
8)肝機能への影響(まれ)
【原因】
肝臓でのホルモン代謝による負担。
【対策】
定期的に検査を受ける。
気になる副作用があれば、ピルに精通したかかりつけの婦人科をもって、相談しながら自分に合うピルを選ぶことが大切です!
安全にピルの服用を始めたい場合は、副作用について事前に医師の説明を受けられるオンライン処方がおすすめです。
次回は、
【2】ピルの安全性(長期間使用しても問題ないの?健康への影響(メリット・デメリット)は?)
について解説します。